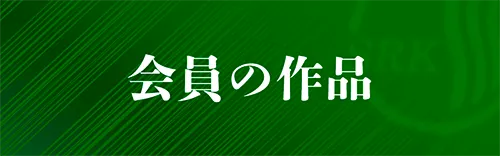川柳人協会主催のイベント紹介
川 柳 人 協 会
川柳人協会では、毎年下記の5つのイベントを主催し、皆様のご参加をお待ちしています。この5つのイベントは、文化の日(11月3日)を中心に行なわれるものと、川柳句集の原典である『誹風柳多留』の出版に関わった方々の追悼句会との二つに大別されます。
なお、それぞれのイベントの応募要項については、その都度このHP上でもご案内いたします。また、全ての入選作品については、年1回発行される会報「川柳文化祭報」に掲載されます。
1 文化の日(11月3日)を中心に行なわれるイベント
1)文化祭川柳大会
川柳人協会が発足して3年後の昭和25年に「第1回京浜川柳大会」が開催されましたが、さらなる川柳の発展と作句・指導力向上を図る一環として、東日本で最も権威のある川柳大会を開催することになり、昭和41年に第1回が文化に相応しい11月3日に開催されました。爾来今日まで延延と続いています。開催日も「文化の日」11月3日で、会場は幾度か変遷しましたが、平成23年度は墨田区の「ユートリア」で行なわれました。昭和42年度より2部制となり1部が当日投句、2部が事前誌上投句でしたが、現在は下記のように2部は大会として独立しています。大会当日には別欄に記載されている川柳文化賞の授賞式も執り行われます。
2)文化祭川柳誌上大会
従来、上記「文化祭川柳大会」の第二部として事前誌上投句で募集していましたが、その存在価値を高めるため、平成21年度より誌上大会として独立したものです。通常、締切は6月15日、発表および入賞者表彰は「文化祭川柳大会」当日の会場にて行なわれます。
●文化祭川柳大会の様子
2 『誹風柳多留』出版に関わる法要句会
1)川柳忌(せんりゅうき)
川柳句集の原典である『誹風柳多留』初編が出版されたのは明和2年(1765)ですが、掲載されている句は、「前句付」の点者(選者)初代川柳が選んだ句から抽出されています。初代川柳は寛政2年(1790)9月23日、73歳で没しましたが、その後、川柳という文芸の名称にもなった初代川柳を法要するため、その命日に旧くから法要行事が行われてきました。明治39年に久良岐社が川柳忌を行なって以降、今日でも9月23日に法要句会が行なわれています。会場は川柳の墓所である台東区・蔵前の龍宝寺で、境内には辞世の句「木枯や跡で芽をふけ川柳」も建立されています。
2)花久忌(はなきゅうき)
「花久」は書肆(書店)・花屋久次郎の略称で、『誹風柳多留』の出版元です。後で記す編者の呉陵軒可有に出版を勧めたのも久次郎だと言われています。可有亡き後の続編の編者も務めました。昭和16年に菩提寺が東岳寺(当時浅草、昭和36年現在の足立区伊興町に越す)であることが判明、過去帳から文化14年(1817)正月晦日に没したと分かりました。以来、功績をたたえ追悼する集りが開かれました。昭和58年からは、命日に近い2月11日(建国記念日)に、菩提寺の東岳寺で行なっています。かつては没句供養も行なわれましたが、今は行なわれていません。境内には花久を顕彰した石碑があり、献句とともに法要が行われます。
なお、同境内には安藤広重の墓と顕彰碑もあります。